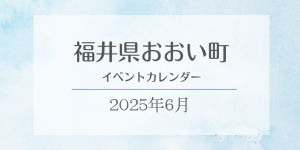-8-1024x576.png)
初夏の贈り物、梅の季節がやってきました
初夏になると訪れるのが梅の季節です。まだ強い日差しが照りつける前の6月中旬にかけて、青梅が収穫の時期を迎えます。この時期になると、市場や直売所に並ぶ鮮やかな緑色の梅の実を見かけることが多くなるでしょう。
「梅仕事」という言葉を耳にしたことはありませんか?これは、旬の梅を使って梅酒や梅干し、梅シロップなどの保存食を作る初夏の風物詩です。日本では古くから、季節の恵みを保存して一年中楽しむ知恵がありました。特に梅は、その酸味と香りを生かした加工品が多く、健康にも良いとされています。しかし現代では、この季節の楽しみを知らない方も増えています。毎年「梅酒を作ってみたいけれど、難しそう」「失敗が心配で始められない」という声をよく耳にします。
おおい町は梅を家庭で栽培されている方も多く、特産品の梅を使って自家製シロップや梅干しを作っている人が本当に多いんです。そんなおおい町から、初心者でも簡単に始められる梅酒と梅シロップの作り方をご紹介します!季節の恵みを自分の手で加工する喜びと、長い期間にわたって楽しめる梅の魅力を、ぜひ今年こそ体験してみませんか?
梅仕事の基本と準備するもの
梅の選び方と下準備のコツ
梅仕事を成功させる第一歩は、良質な梅を選ぶことから始まります。梅酒や梅シロップ作りに最適なのは、完全に熟す前の硬い青梅です。市場に出回り始める5月下旬から6月中旬が最適な時期とされています。選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 鮮やかな緑色で、傷や変色がないもの
- 実がしっかりと固く、張りがあるもの
- サイズが均一なもの
- できれば農薬が少ない、有機栽培のもの
梅の品種としては、「南高梅」や「白加賀」が香りや果肉の厚さから人気がありますが、おおい町で採れる品種「紅映(べにさし)」が特におすすめです。

梅を入手したら、すぐに下準備を行いましょう。青梅は日持ちしないため、購入したその日のうちに作業することをおすすめします。準備の手順は以下の通りです。
- 梅を水で洗い、汚れをしっかりと落とす
- 水気を拭き取り、天日に半日ほど干す(アク抜きと殺菌効果があります)
- ヘタを爪楊枝などで丁寧に取り除く
- 再度水分を拭き取る
この下準備をしっかりと行うことで、雑菌の繁殖を防ぎ、えぐみが出ず、長期保存に適した状態になります。
揃えておきたい道具と材料
梅酒と梅シロップを作るには、以下の道具と材料を準備しましょう。
共通の道具:
- 保存用の密閉ガラス瓶(梅酒用の大きめのもの、または梅シロップ用の中サイズのもの)
- キッチンペーパーまたは清潔な布巾
- 計量カップ
- はかり
- 清潔なトング(梅を取り扱うため)
梅酒の材料(1.8L瓶1本分):
- 青梅 1kg
- 氷砂糖 500g〜800g(お好みの甘さで調整)
- ホワイトリカー(35度) 1.8L
梅シロップの材料(1L瓶1本分):
- 青梅 500g
- 砂糖 500g
- レモン 1個(お好みで)
保存容器は必ず煮沸消毒するか、アルコールでしっかりと殺菌しましょう。また、梅酒用のホワイトリカーは35度のものを選びます。度数が低すぎると雑菌が繁殖する可能性があり、高すぎると梅の成分が十分に抽出されないことがあります。
砂糖は白い砂糖であれば種類は問いませんが、梅酒には溶けやすい氷砂糖がおすすめです。梅シロップには粒の細かいグラニュー糖や上白糖が使いやすいでしょう。
さわやか梅シロップの作り方
梅シロップは、アルコールを使わず砂糖だけで梅のエキスを抽出したものです。お子様やアルコールが苦手な方も楽しめる、夏の暑い季節にぴったりの清涼飲料水を作ることができます。基本の作り方は以下の通りです。
- 消毒した保存瓶に、下準備をした梅を入れる
- 砂糖を加える(梅と同量が基本)
- 蓋をしっかりと閉め、冷暗所で保存する
- 1日1回、瓶を軽く振って砂糖を溶かす
- 1週間程度で梅から水分が出て、シロップ状になる
- お好みでレモンを加えると、香りが良くなり、保存性も高まる
梅シロップは早ければ1週間程度で完成します。梅から水分が出て砂糖が完全に溶けたら飲み頃です。冷蔵庫で保存し、冷水や炭酸水で割って楽しみましょう。
梅シロップ作りのポイント
より美味しい梅シロップを作るためのポイントをいくつかご紹介します。
糖度の調整: 基本的には梅と砂糖を1:1の重量比で作りますが、より甘いシロップがお好みなら砂糖を多めに、さっぱりとした味わいがお好みなら少なめにするとよいでしょう。
レモンの活用: レモンを加えることで、クエン酸が増え保存性が高まるとともに、爽やかな香りが加わります。レモンは皮ごと輪切りにして加えるか、皮をむいて果肉だけを加えるか、お好みで選べます。
保存方法: 完成した梅シロップは冷蔵庫で保存し、なるべく早めに使い切ることをおすすめします。1ヶ月以上の長期保存を考える場合は、しっかりと殺菌した瓶を使用し、シロップを一度沸騰させてから冷やし、瓶詰めするとよいでしょう。

梅シロップの活用法
完成した梅シロップは様々な方法で楽しむことができます。以下に、活用アイデアをいくつかご紹介します。
梅ソーダ: 最も一般的な飲み方です。グラスに氷を入れ、梅シロップを適量注ぎ、炭酸水で割るだけで、爽やかな梅ソーダの完成です。レモンスライスを添えると見た目も華やかになります。
梅ヨーグルト: プレーンヨーグルトに梅シロップをかけるだけで、簡単に美味しいフルーツヨーグルトになります。朝食やデザートにぴったりです。
かき氷シロップ: 夏のかき氷に梅シロップをかければ、市販のシロップとは一味違う、本格的な梅風味のかき氷を楽しめます。
ドレッシング: 梅シロップに醤油や酢、オリーブオイルを加えれば、さっぱりとした和風ドレッシングの完成です。サラダはもちろん、冷しゃぶや冷奴にもよく合います。
お菓子作り: ゼリーやアイスクリーム、プリンなどのデザート作りにも活用できます。砂糖の代わりに梅シロップを使うことで、爽やかな酸味のあるスイーツに仕上がります。
梅シロップを漬けた後の梅も捨てずに活用しましょう。砂糖に漬けた梅は「梅シロップ梅」として、そのままデザートやヨーグルトのトッピングとして楽しめます。また、細かく刻んでジャムのようにしたり、乾燥させて梅干し感覚で楽しむこともできます。
基本の梅酒の作り方
梅酒は日本の伝統的な果実酒であり、作り方もシンプルです。数ヶ月から1年ほど熟成させることで、まろやかな味わいに変化していきます。基本の作り方は以下の通りです。
- 消毒した保存瓶に、下準備をした梅を入れる
- 氷砂糖を加える
- ホワイトリカーをゆっくりと注ぐ
- 蓋をしっかりと閉め、冷暗所で保存する
- 1週間に1回程度、瓶を軽く振って砂糖を溶かす
- 最低3ヶ月、できれば半年から1年熟成させる
梅酒は時間が経つほど味がまろやかになります。忍耐が必要ですが、自家製の梅酒は市販品とは一味違う深みがあり、待つ価値は十分にあります。

梅酒作りのポイント
より美味しい梅酒を作るためのポイントをいくつかご紹介します。
糖度の調整: 甘さは好みによって大きく異なります。標準的には梅1kgに対して氷砂糖500g〜800gですが、甘いものがお好きな方は多めに、さっぱりとした味わいがお好みなら少なめにするとよいでしょう。
漬け込む時期: 梅酒は暑くなる前の5月下旬から6月中旬に漬け始めるのが理想的です。この時期の梅は青く、果肉が硬く、香りも良いため、高品質の梅酒ができます。
保存環境: 直射日光を避け、冷暗所で保存することが重要です。温度変化の少ない場所を選びましょう。瓶に日付や内容物のラベルを貼っておくと、複数の瓶を作った場合も管理しやすくなります。
熟成期間: 梅酒は時間をかけるほど味わいが深まります。最低でも3ヶ月、理想的には1年以上熟成させると、まろやかで芳醇な味わいになります。長期熟成用と短期用で分けて作るのも一つの方法です。
アレンジレシピで広がる梅酒の世界
基本の梅酒に少し手を加えることで、オリジナリティあふれる味わいを楽しむことができます。以下にいくつかのアレンジレシピをご紹介します。
はちみつ梅酒: 氷砂糖の代わりにはちみつを使用します。まろやかな甘さと、はちみつ特有の風味が加わります。ただし、はちみつを使う場合は雑菌の繁殖リスクが高まるため、アルコール度数が40度のホワイトリカーや焼酎を使うことをおすすめします。
スパイス梅酒: シナモンスティックやバニラビーン、スターアニスなどのスパイスを加えることで、香り高い梅酒になります。スパイスは途中で取り出すことも可能なので、香りを確認しながら調整するとよいでしょう。
フルーツミックス梅酒: 梅と一緒に他の果物(さくらんぼ、いちご、りんごなど)を漬け込むことで、フルーティーな香りと味わいを楽しめます。季節の果物を活用して、オリジナルの果実酒を作りましょう。
黒糖梅酒: 氷砂糖の代わりに黒糖を使うと、深みのある味わいの梅酒ができます。沖縄産の黒糖を使うと、ミネラル豊富で独特の風味を持つ梅酒に仕上がります。
アレンジは自分の好みや感性を生かして楽しみましょう。自分だけのオリジナル梅酒は、贈り物にしても喜ばれること間違いありません。
梅仕事カレンダー:おおい町の梅の旬と収穫
福井県おおい町は、若狭地方特有の温暖な気候と海からの潮風の影響で、品質の良い梅が育つ地域として知られています。おおい町での梅の収穫時期と、地域での梅に関する情報をご紹介します。
おおい町での梅の収穫は、通常5月下旬から6月中旬にかけて行われます。気候条件によって多少前後することがありますが、例年この時期に市場や直売所に地元産の青梅が並び始めます。おおい町の梅は、酸味と香りのバランスが良く、梅酒や梅シロップ作りに最適とされています。
おおい町内の直売所では、この時期になると地元で採れた新鮮な青梅を購入することができます。道の駅や農産物直売所を訪れると、時期によっては農家の方から梅の選び方や保存方法についてアドバイスをもらえることもあります。

今年も【梅まつり】の開催が決定しました!
2025年6月15日(日)9:00〜 道の駅うみんぴあ大飯にて
梅詰め放題や梅を使った商品の試食会を予定しております!
ぜひお越しくださいね。
また、おおい町では毎年梅の時期に合わせて、梅収穫体験などのイベントや梅シロップ作りイベントなども開催されています。地元の伝統的な梅の加工方法を学べる貴重な機会ですので、関心のある方はぜひ参加してみてください。

梅仕事を始める際の目安となるカレンダーは以下の通りです:
- 5月下旬~6月中旬:青梅の収穫・購入適期
- 6月:梅酒・梅シロップ作り
- 7月~8月:梅シロップを活用した夏の涼味を楽しむ
- 9月~10月:梅酒の中間チェック(味見)
- 12月~1月:熟成した梅酒を冬の温まり酒として楽しむ
- 3月~4月:ほぼ1年熟成した梅酒の完成
季節ごとの梅の楽しみ方を知ることで、一年を通じて梅の恵みを味わうことができます。
梅しごとで四季を感じる暮らし
梅仕事は単なる保存食作りではなく、日本の四季を感じる暮らしの知恵でもあります。季節の移ろいとともに変化する梅の楽しみ方をご紹介します。
初夏:5月から6月にかけての初夏は、青梅が出回る時期です。この時期に梅酒や梅シロップを仕込むことで、一年間の梅の恵みへの準備が始まります。新緑の美しい季節に、爽やかな香りの青梅を手に取るのは、日本の初夏の風物詩と言えるでしょう。
夏:暑い夏には、梅シロップを使った冷たい飲み物が最高の涼味をもたらします。梅ソーダやかき氷は、夏バテ防止にも効果的です。また、梅酒を冷やして飲めば、さっぱりとした果実酒として楽しめます。
秋:実りの秋には、梅酒の中間チェックをしてみましょう。漬けてから3〜4ヶ月経った梅酒は、まだ若々しい味わいながらも、徐々に熟成の兆しが見え始めます。この時期の梅酒は、秋の夜長にちょうど良い一杯となるでしょう。
冬:寒い冬には、熟成した梅酒をお湯割りにして飲む「梅酒の温もり酒」がおすすめです。体を芯から温め、風邪予防にも効果があると言われています。また、梅酒に漬けた梅の実をお菓子作りに活用すれば、冬のティータイムが一層豊かになります。
春:新しい季節の訪れとともに、約1年熟成した梅酒が完成します。この時期の梅酒は、まろやかで深みのある味わいに変化しており、特別な日の食前酒として楽しむのがおすすめです。また、新しい年の梅仕事に向けて、空いた瓶の準備も始まります。
このように梅仕事は、日本の四季の移ろいを感じながら、一年を通じて楽しむことができる素晴らしい食文化です。現代の忙しい生活の中でも、こうした季節の営みを取り入れることで、より豊かな暮らしを実現することができるでしょう。
まとめ:今年こそ始めよう、梅しごと
梅の季節は短く、あっという間に過ぎていきます。「今年こそ梅仕事を始めたい」と思いながらも、毎年タイミングを逃してしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、この記事でご紹介したように、梅酒や梅シロップ作りは特別な技術や道具がなくても、誰でも簡単に始めることができます。
梅仕事の魅力は、自分の手で季節の恵みを加工し、長期間にわたって楽しめること。また、手作りの梅酒や梅シロップは市販品にはない深みがあり、贈り物にしても喜ばれます。さらに、毎年少しずつアレンジを加えることで、自分だけのオリジナルレシピを確立していく楽しさもあります。
おおい町の新鮮な青梅を使って、今年こそ梅仕事を始めてみませんか?初夏の思い出とともに瓶に閉じ込めた梅の香りと味わいは、一年を通じてあなたの食卓を豊かに彩ることでしょう。梅仕事が日本の伝統的な食文化として、これからも多くの家庭で受け継がれていくことを願っています。

17年ぶりに生まれ故郷のおおい町に地域おこし協力隊として戻ってきました。
こどもの頃は山や川で遊ぶのが大好きでした。
起きたら聞こえる鳥のさえずりや車を走らせていると見えるキラキラ輝く海など
日常の風景が幸せに満ちているおおい町の魅力をみなさんにお伝えしたいと思います。

-8-300x169.png)